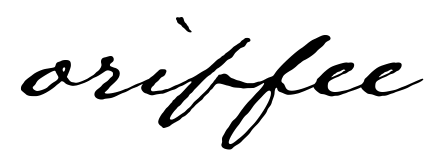いよいよ夏本番に突入し、急冷式アイスコーヒーが美味しい季節になってきた。そこで、昨年紹介したオリジナルレシピを刷新した2022年バージョンを記事にまとめていこう。
ただし、すでに多くの人が急冷式のレシピを紹介してきてるので、この記事では、アイスコーヒーを淹れるために僕が使うコーヒー器具を紹介しつつ、美味しい淹れ方もお届けしたい。
そもそも “急冷式” のアイスコーヒーとは?


アイスコーヒーには淹れたてのコーヒーを冷やす【急冷式】と、水で成分を抽出する【水出し】の2つがあり、今回紹介するのは急冷式。名前のとおり、氷で急速に冷やしたコーヒーのことで、フレッシュで爽やかな風味が特徴だ。
コーヒーを急速に冷やすことで良い香り成分を逃さず閉じ込め、豊かなフレーバーを長時間楽しむことができる。低温でじっくり成分を引き出す水出しコーヒーとは違い、すぐ冷えるので飲みたい時にいつでもの楽しめるのも嬉しい。
急冷式アイスコーヒーのレシピ

実際にコーヒーを淹れながら抽出方法を説明する前に、急冷式アイスコーヒーのレシピを簡単に紹介しておこう。
● 急冷式アイスコーヒーのレシピ (1杯分)
■材料
⚪︎コーヒー粉 (中細挽き):20g
⚪︎お湯 (90~93度):160ml
⚪︎ 氷:150g以上
■淹れ方 (30秒ごとに40mlずつ)
【1投目】0:00 40ml のお湯をコーヒー粉全体に浸透させる
【2投目】0:30 40ml を中央から外側へ注いでいく
【3投目】1:00 40ml を中央から外側へ注いでいく
【4投目】1:30 40ml を中央から外側へ注いでいく
■抽出時間
2分20〜2分30秒ほど
今回は中深煎りの豆を使用したレシピとなっているので、浅煎りの場合はコーヒー粉を21gにしたり、挽き目を気持ち細く。深煎りだと豆を19gにしたり、挽き目を気持ち粗くすると良い。でも最初はこのレシピで淹れてみてほしい。
急冷式アイスコーヒーを淹れていく !
それでは実際に1杯分の急冷式アイスコーヒーを淹れていこう。急冷式は通常より濃いコーヒーを落とし、氷で薄まってちょうど良い濃さになる。濃い目に淹れるのがポイントだ。

まずは氷を入れる。多いに越したことはないため、150g以下にならないようにだけ気を付けよう。抽出が終わる頃には100gほどが溶けるので、合計250ml弱のアイスコーヒーを飲める計算だ。
40ml をコーヒー粉全体に浸透させる


蒸らしで意識するのは、コーヒーの粉にお湯を浸透させること。2投目以降で美味しい成分を引き出しやすくするための下準備だ。
1投目でお湯とコーヒー豆が混じり合うと、豆に含まれる二酸化炭素が放出される。蒸らしでは、コーヒー豆の成分よりも先に二酸化炭素を放出させ、2投目で美味しい成分を引き出すための道をつくるのがポイント!

全てのコーヒー粉から二酸化炭素を放出させるためにも、お湯を注いだ直後にドリッパーを3周ほど大きく揺らすのも欠かせない (スプーンで5回ほどかき混ぜる方が確実だけど、少し手間なので僕は揺することが多い) 。

蒸らすときにコーヒー粉が膨らむのは、前述したようにコーヒー豆に含まれる二酸化炭素が放出されているから。焙煎したての豆には二酸化炭素が多く含まれてるため、より膨らむ。
40ml を中央から外側へ注ぐ


お湯を多く注ぐほど成分を抽出できるため、今回のように少ないお湯で抽出する場合はとくに甘さが抽出されにくい。甘さをしっかり引き出すためにも、粉を細く挽いて表面積を広くし、成分を溶け出しやすくするのが大切だ。
40ml を中央から外側へ注ぐ


3投目を注ぐ頃にはコーヒー豆に含まれる美味しい成分は減ってきている。なので注ぐお湯の勢いを少し強めにし、水流の力で残りの美味しい成分を引き出すようにする。
40ml を中央から外側へ注ぐ


4投目を注ぎ終えると、ドリッパーを軽く2回ほど円状に揺すってあげて、お湯が落ち切るとコーヒー粉が平らになるようにする (平らになるということは、お湯がポタポタと落ち切るギリギリまで全ての粉がお湯と触れ合い、成分が抽出されるということ) 。

なお抽出時間が2分半以上経ってる場合は、余分な成分まで抽出されてるように感じる。抽出が長引く場合はコーヒーが完全に落ち切る前にドリッパーを上げてしまおう。そうではない場合は落ち切るまで待つ。

アイスコーヒーを注ぐ際、サーバー内の氷は溶けやすくなっているのでグラスの中に新しい氷を入れておくのがおすすめ。
このレシピで淹れてみて薄かった場合は、お湯の温度を1~2度上げてみたり、挽き目を細かくしてみよう (濃かった場合は温度を下げて、挽き目を粗くする) 。
急冷式におすすめのコーヒー器具6選

- HARIO | V60 ドリッパー
- KRUVE | Brew Stick
- OREA | Sence Carafe
- HARIO | V60 コーヒースケール
- 1Zpresso | JXpro コーヒーグラインダー
- FELLOW | Stagg Pour-Over Kettle
最後に、急冷式アイスコーヒーを淹れるのにおすすめの器具を紹介しておこう。ただし基本的にはホットコーヒーを淹れるときの器具でOK。参考程度に読んでみてほしい。
HARIO | V60 ドリッパー


急冷式は細く挽いたコーヒー粉を多く使う分、お湯の勢いが遅くなり、抽出に時間がかかりがち。なので V60ドリッパーや ORIGAMI 、そして淹れ方の説明でも使った OREA Brewer V3 など、お湯が流れ落ちるスピードが速いものがおすすめ。
KRUVE | Brew Stick


蒸らしでコーヒー粉をお湯に浸透させ、成分を無駄なく引き出すために使いたいのが KRUVE (クルーヴ) の『Brew Stick』。前述のとおりドリッパーを揺するだけでもいいけれど、しっかり蒸らすなら手間だが使いたい。
コーヒー粉が多いと、ドリッパーの下部分でダマになってしまう。Brew Stick を使うときは5回ほど前後に動かして、粉を攪拌してあげよう。
OREA | Sence Carafe


サーバーは正直好みでOK。ただ容量が300ml以上あるものをマストで使おう。僕が記事執筆時点で愛用している OREA の『Sence Carafe』は、底枠が滑らかな曲線を描くためサーバーを揺らすと氷ごと攪拌しやすい。
とはいえそれだけの理由で急冷式アイスコーヒー用に使ってるので、本当、自分が好きなデザインのものを選んで良いと思う。
HARIO | V60 コーヒースケール


氷や結露が伴うアイスコーヒーには、電池式でタフな HARIO の『V60 コーヒースケール』がおすすめ。Amazon での価格は記事執筆時点だと4,252円 (税込) とかなり安い。初めてのコーヒースケールにも最適だ。
1Zpresso | JXpro コーヒーグラインダー


これまで色々試した中で、一番コスパが良いのが 1Zpresso の『JXpro コーヒーグラインダー』。価格は Amazon で24,380円と高いけれど、同ブランドでコーヒーミル界の最高峰『JPpro』と比較してもなんら遜色ない。
コーヒー粉が均一で微粉も少ないので、粉がだまになりづらい。またスムーズにお湯が流れるので、安定した味わいのコーヒーを淹れることもできる。コーヒーの味に最も直結すると言われるグラインダーにこだわりたい人には勧めたい。
FELLOW | Stagg Pour-Over Kettle


強すぎず、弱すぎない勢いでお湯を注げる FELLOW の『Stagg Pour-Over Kettle』は急冷式アイスコーヒーにおすすめ。お湯の勢いが強すぎると粉を突き抜けてしまったり、弱すぎると抽出までに時間がかかり雑味の原因になってしまう。
FELLOW のポットは角度をかなり傾けて注いでも、ちょうど良い湯量の印象がある。なお値は張るものの、電気ケトルバージョンもあるのでより快適に FELLOW ポットを使いたい人にはおすすめ。
FELLOW | Stagg Pour-Over Kettle
まとめ

こんな感じで急冷式アイスコーヒーの淹れ方とおすすめ器具を紹介してみた。僕のレシピは30秒ごとに40mlのお湯を注ぐだけのシンプルレシピなので、正確な時間を思い出す必要がなく、ドリップに集中しやすいものとなっている。
またこれは急冷式アイスコーヒーに限った話ではないが、お気に入りのコーヒー器具で淹れるとドリップ体験は格段に楽しくなる。上記で器具を紹介したけど、自分が気に入ってるものがあればそれが一番。素敵なコーヒー時間を!